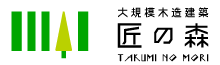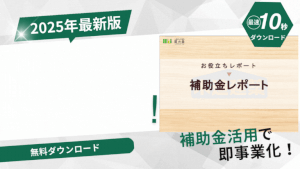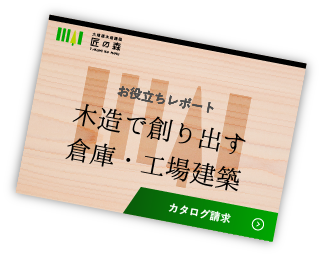みなさんこんにちは。福岡県久留米市の大規模木造建築専門店の匠の森です。
「地域に貢献できる障がい者グループホームを作りたいが、何から手をつけていいか分からない」「グループホームの作り方について、設立の手順や満たすべき基準を具体的に知りたい」このような、グループホームの作り方に関するお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか。
障がいを持つ方々が地域社会で安心して暮らせる場を提供するグループホームの設立は、非常に社会的意義の大きな事業です。しかし、その作り方は複雑で、法人設立から物件の準備、行政への申請まで、多くのステップと専門知識が求められます。この記事では、障がい者グループホームの作り方について、設立から開設までの具体的な流れ、そして必ず遵守しなければならない人員・設備基準などを、大規模木造建築のプロの視点も交えながら、網羅的に解説していきます。
この記事を最後までお読みいただくことで、グループホームの作り方の全体像が明確になり、設立に向けた具体的な準備をスムーズに進められるようになります。障がい者グループホームの開設を志す事業者様は、ぜひ最後まで読んでみてください!
グループホームの作り方を学ぶ前の基礎知識
グループホームの具体的な作り方に入る前に、まずはその基本的な定義と、設立の前提条件を理解しておくことが重要です。
障がい者グループホーム(共同生活援助)とは?
障がい者グループホームとは、正式には「共同生活援助」と呼ばれる障害福祉サービスの一つです。障がいを持つ方々が、専門スタッフによる支援を受けながら、地域の中にある一軒家やアパートなどで共同生活を送るための住まいのことを指します。入居者一人ひとりの自立した生活を尊重し、家庭的な雰囲気の中でサポートを提供することが、この事業の核となります。
グループホームを作るために必要な法人格
グループホームの作り方として、まず大前提となるのが「法人格」の取得です。個人で障がい者グループホームを運営することはできず、必ず「株式会社」「合同会社」「NPO法人」「社会福祉法人」などの法人格を持っている必要があります。これから事業を始める方の多くは、まず法人を設立するところからスタートします。
失敗しないグループホームの作り方|7つのステップと流れ
グループホームの作り方は、思い立ってすぐに完成するものではありません。行政との協議を重ねながら、計画的に準備を進める必要があります。ここでは、設立準備から開設までの作り方を、7つのステップで具体的に解説します。
ステップ1:法人設立と事業計画の策定
グループホームの作り方の第一歩は、運営母体となる法人を設立することです。定款の作成や登記申請など、司法書士などの専門家のサポートを受けながら進めるとスムーズです。並行して、「どのような障がいのある方を対象に、どのような支援を提供したいのか」という事業の根幹となるコンセプトを固め、詳細な事業計画書を作成します。
ステップ2:指定権者(行政)との事前協議
事業計画の骨子が固まったら、事業所を設置する市町村の障がい福祉担当課(指定権者)へ事前協議の申し込みを行います。この協議では、事業計画の内容が地域のニーズに合っているか、人員や建物の計画が基準を満たしているかなどについて、行政の担当者とすり合わせを行います。この事前協議が、その後の作り方を円滑に進めるための非常に重要なプロセスとなります。
ステップ3:物件の選定と確保
グループホームを作るための物件を確保します。既存の一軒家やアパートを賃貸または購入する方法と、新たに土地を購入して新築する方法があります。物件は、後述する「設備基準」をクリアしている必要があります。特に新築の場合は、基準を満たしつつ、入居者が快適に過ごせる空間づくりが求められます。
ステップ4:資金調達と補助金の申請
事業計画に基づいて、自己資金に加えて必要な資金を調達します。日本政策金融公庫や福祉医療機構(WAM)からの融資が一般的です。また、グループホームの作り方において、補助金の活用は欠かせません。建物の整備費用などを補助する制度があるため、必ず行政の担当窓口に相談しましょう。
ステップ5:人員の確保と研修
管理者やサービス管理責任者、世話人、生活支援員など、後述する「人員基準」を満たすためのスタッフを採用し、開設に向けた研修を行います。質の高い支援を提供できるチーム作りが、グループホームの評判を左右します。
ステップ6:運営に必要な備品の準備
建物とスタッフが揃ったら、運営に必要な備品を準備します。ベッドや家具、家電、厨房機器、火災報知器などの消防設備、事務用品まで、リストアップして計画的に揃えていきましょう。
ステップ7:指定申請と事業所の開設
すべての準備が整ったら、行政に事業者としての「指定申請」の書類を提出します。書類審査と、担当者が実際に現地を訪れて設備などを確認する現地確認を経て、問題がなければ指定事業者として認可され、グループホームを開設できます。
グループホームの作り方で遵守すべき3つの基準
グループホームの作り方において、最も重要なのが、障害者総合支援法で定められた「人員基準」「設備基準」「運営基準」の3つを必ず満たすことです。
1. 人員基準
グループホームを運営するために必要な職員の職種と人数に関する基準です。管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員などを、入居者の人数に応じて適切に配置する必要があります。
2. 設備基準
建物の構造や広さ、備えるべき設備に関する基準です。主な基準には以下のようなものがあります。
- 立地: 住宅地の中など、地域住民と交流しやすい場所であること。
- 定員: 1つの共同生活住居の定員は原則2人以上10人以下。
- 居室: 居室一つの広さは7.43㎡(約4.5畳)以上であること。
- 設備: トイレ、洗面所、お風呂、台所など、生活に必要な設備を備えていること。
- バリアフリー: 廊下の幅や段差の解消など、障がいのある方が安全に生活できる配慮が求められます。
弊社が以前、建築したグループホームでは木造建築のため、これらの設備基準を満たしつつ、木の温もりを活かした家庭的で温かい雰囲気の空間を実現でき、事業者様にも入居者様にも大変満足いただけた経験がございます。
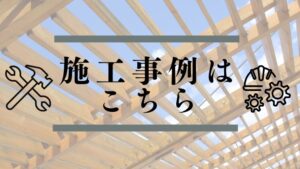

3. 運営基準
事業者がグループホームを運営する上で、遵守すべきルールに関する基準です。入居契約の内容や、個別支援計画の作成、利用者からの苦情への対応、非常災害時の対策などが定められています。
まとめ
障がい者グループホームの作り方は、法人設立から始まり、事業計画、行政協議、物件確保、資金調達、人員確保、そして指定申請と、多くのステップを踏む必要があります。そのすべての過程で、法律で定められた「人員」「設備」「運営」の3つの基準を遵守することが、成功への大前提となります。
特に、入居者の方々が日々を過ごす「建物」は、事業の質を左右する最も重要な要素です。設備基準をクリアするだけでなく、いかに入居者が「我が家」として安心して快適に暮らせる空間を提供できるかが、選ばれるグループホームになるための鍵となります。
私たち匠の森は、福岡県久留米市を拠点に、大規模木造建築の豊富な実績とノウハウを活かし、グループホームのような福祉施設の建築を得意としています。木造建築は、コストを抑えながらも、木の温もりと優れた断熱性・調湿性で、入居者にとって心と身体に優しい理想的な住環境を提供できる構造です。グループホームの作り方でお悩みの際は、ぜひ一度、私たちにご相談ください。開設から建築、運営までトータルサポートいたします。
まずは無料カタログをダウンロードください!